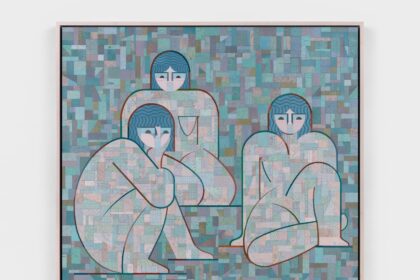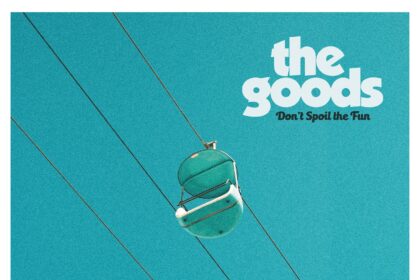MUSAC(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León/カスティーリャ・イ・レオン現代美術館)は、ヨーコ・オノの実践を大規模に俯瞰する展覧会を行う。約1,700㎡にわたり70点超の作品が集結し、パフォーマンス、コンセプト/参加型アート、映画、サウンド、インスタレーション、絵画、写真を横断する歩みを追跡する。展覧会タイトル「Yoko Ono. Insound and Instructure」は、作家初期の一場面を想起させつつ、本展の基調を端的に示す。すなわち、長年にわたり彼女の創作を支えてきた「インストラクション(指示)に基づく形式」と音の結合である。ここで優先されるのは物質ではなく「アイデア」だ。――提案、スコア(楽譜)、招待状としてのアートである。
キュレーションはジョン・ヘンドリックス、コナー・モナハン、アルバロ・ロドリゲス・フォミナヤの三名が担当。近年スペインで開催されたヨーコ・オノの個展のなかでも屈指の規模で、形成期から成熟期へと至る作品を、カノン化された代表作、参加型の環境、比較的新しいインスタレーションを交差させながら配置する。全体を通じて示されるのは、メディアの広がりだけではない。作品の実現・完了における観客の能動的役割という、オノの仕事を貫く軸が明確に立ち上がる。
出品作には、パフォーマンスおよびコンセプチュアル・アートの言語を形づくった初期の画期が複数含まれる。観客を共同の作者へと呼び込むインストラクション作品「Voice Piece for Soprano」や「Draw Circle Painting」(公共の参加によって初めて成立する)と呼応するかたちで、「Cut Piece」が提示される。また、歩行可能な迷路「A MAZE」や、プロローグであり宣言でもある建築的な閾(しきい)「EN TRANCE」といった参加型環境も展開される。これらを通過することで、観客はオノの「指示」が、歩く、聴く、話す、選ぶといった身体的状況へと開かれていく過程を体験する。芸術は単なる鑑賞の対象ではなく、「注意とエージェンシー(主体性)の実践」へと変換される。

本展は、すでに定評のある章にとどまらない。比較的近作を組み込むことで、数十年にわたって反復されてきた主題の連続性が可視化される。「DOORS」と「INVISIBLE FLAGS」は、平和、社会的想像力、馴染み深い構造やシンボルの再配置に向けられたオノの関心をさらに拡張する。ここでも、簡潔な身振りと最小限の指示が機能の核となり、小さな知覚のずれがいかに共同的な省察の場をひらくのかを考えるよう促す。
映画は、彼女の実践における主要な柱である。ジョン・レノンとの協働および単独で制作された「Rape」「Fly」「Freedom」などが精選され、親密さと露出、「見る/見られる」ことの政治、時間の経過に伴う知覚の可塑性といった問いが前景化される。インストラクション作品や参加型環境と並置されることで、オノの方法におけるメディア横断の一貫性はいっそう明瞭になる。ページ、展示空間、スクリーン――どの場であれ、作品は多くの場合、言語から立ち上がる。短い命題、ひとつのスコア、出来事の条件を設定する一行の指示。結果として生じるのは、閉じたプロダクトではなく「活性化された状況」にほかならない。
レオンでの今回のプレゼンテーションは、オノのレガシーを再読しようとする、より広い制度的潮流のなかに位置づけられる。大規模な美術館が相次いで彼女の仕事を本格的に取り上げてきた事実は、参加、オーサーシップ、アクティヴィズム、そして芸術の社会的役割をめぐる今日的な議論において、彼女の実践がなお有効であることを示す。本展は、その文脈のもと、初めて触れる観客には導入として、既知の主要作に親しむ観客には深化した邂逅として機能し、オノを戦後美術の周縁ではなく、概念的・パフォーマティヴな中核へと据え直す。
短い伝記的な枠組みは、本展を駆動する「指示にもとづく方法」の展開を見通す助けとなる。東京に生まれたオノは、ニューヨークに拠点を定める前に米国で形成期を過ごした。学習院大学哲学科に初の女性として入学し、その後サラ・ローレンス大学で学ぶ。アーティストと作曲家の重なり合うコミュニティにおいて、彼女は慣習的なオブジェよりもアイデアとスコアを優先し、観客に「作品を行為へと移す」ことを促す実践を築いた。
ニューヨークのロウアー・マンハッタンでは、作曲家ラ・モンテ・ヤングとともに、同市の実験的シーンの形成に決定的な役割を果たしたパフォーマンスやイベントを組織した。AGギャラリーでの初個展では、今日では象徴作とされる「Painting to Be Stepped On」を含む「Instruction Paintings」を発表。カーネギー・リサイタル・ホールでは、動き・音・声を交差させた作品を上演した。東京に戻ると、草月アートセンターで新作パフォーマンスを行い、物質的オブジェをアイデアに置き換える――文字による指示のみで構成される――制作への決定的な転回を確かなものにした。この時期、ジョン・ケージやデイヴィッド・チューダーとともにツアーを行い、実験音楽と美術の交差点をさらに深めた。著書『Grapefruit』は、このアプローチの精神を、凝縮されたスコア集として結晶させている。
ニューヨークへ復帰後も、オノはイベントの企画、郵便や広告を介した介入、インストラクションにもとづく映画脚本の執筆、自作の短編制作を継続した。ロンドンへの招待は、デストラクション・イン・アート・シンポジウム周辺のアーティストとの交流を生み、インディカおよびリッソン・ギャラリーでの展示へとつながった。コンセプチュアルなオブジェ「White Chess Set」「Apple」「Half-A-Room」は、「Film No. 4 (Bottoms)」の新ヴァージョンや「Music of the Mind」シリーズと並置されて紹介される。インディカ・ギャラリーでのジョン・レノンとの出会いは、美術・映画・音楽を横断し、公共空間やメディア空間へと可視的に広がるアクティヴィズムをも伴う創造的な協働の出発点となった。
レノンとともに、オノの概念的戦略は「WAR IS OVER! If you want it」キャンペーンや、ベッド・イン・フォー・ピースといった高い可視性をもつ平和運動へと拡張された。これらの行為は、インストラクションのロジックを市民的領域へと移し替えるものでもあった。以後、彼女はソロおよび共同名義のアルバムを多数発表し、「FLY」「Freedom」「Rape」「Apotheosis」「Imagine」といった映画を制作。制度とコンセプトの身振りの境界を問い直すミュージオロジーの実験も構想した。個人的な動揺に彩られた時期に、音楽が支えであったとする本人の言葉は、本展の叙述を補強する。
視覚芸術に対する制度的関心も着実に高まっていった。ホイットニー美術館でのプレゼンテーションを機に、ジャパン・ソサエティ・ギャラリーが企画し国際巡回した回顧展「Yes Yoko Ono」が続く。アイスランド・ヴィズエイ島に建立された IMAGINE PEACE TOWER は、平和への共同のコミットメントを永続的な記念碑として具体化した。ヴェネツィア・ビエンナーレでの生涯功労賞に加え、各時期の素材を再解釈する新作アルバム、大規模美術館――ニューヨーク近代美術館、東京都現代美術館、テート・モダン、ノイエ・ナショナルギャラリー――での展覧会は、彼女の実践が同時代の言説において持つ重みを改めて確証する。
MUSAC の展示構成は、「指示」という親密なスケールと、「環境」という建築的スケールを精密に接続する。「EN TRANCE」のエントランス通路は、阈・変容・遊戯という展覧会のキーワードを空間的経験へと凝縮する蝶番のように機能する。「A MAZE」は、短いスコアの論理を身体の運動へと翻訳し、観客を単なる観察者ではなく、空間を航行する存在として招き入れる。その意味で本展は、オノのアイデアがフォーマットを横断して増殖していく様を示す「実践マニュアル」としても読める。ひとつの指示は、口頭の行為、撮影された身振り、室内スケールのインスタレーション、あるいは読者の想像力を起動する紙上の静かな提案へと派生しうるのだ。
この通底線は、形式面にとどまらない。芸術が社会的想像力の媒体となりうるというオノの確信が、今回集められた作品群全体を支えている。「DOORS」は、日用品を私的/公的、閉/開という状態を往還する「移行の通路」として再配置し、「INVISIBLE FLAGS」は政治的象徴をその最小の理念へと還元して、帰属・ネーション・責任についての思考を促す。これらの作品は「何を考えるべきか」を指示しない。むしろ、知覚のささやかな偏差が広がりをもって反復されるとき、共同の生活の織り目そのものがいかに変容しうるかを熟考するよう求める。時間とメディアを横断して、その野心を誇張なく可読に保っている点こそ、本展の達成である。
総じて「Yoko Ono. Insound and Instructure」は、早くから脱物質化へ向かいながら、その社会的帰結を見失わなかった一つの実践を提示する。映画・サウンド・空間を横断して指示、スコア、提案を展開することで、作品が概念的・政治的・形式的に「開かれた」まま、明確な構造を保持しうることを実証する。同時に、観客を協働者として再確認し、作者性の外縁を拡張する。オノの仕事の中心命題でもあるこのテーゼは、本展の持続的な論点でもある。すなわち、ひとつの指示に耳を澄ませ、次の一歩を選ぶという単純な行為から、変化を構想し試みる触媒としての芸術が始動する。
会場・会期:MUSAC(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)— 11月8日から2026年5月17日まで。キュレーター:ジョン・ヘンドリックス、コナー・モナハン、アルバロ・ロドリゲス・フォミナヤ。