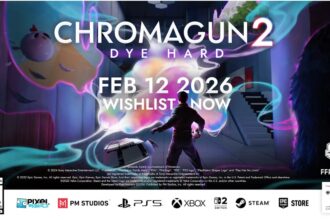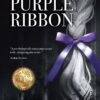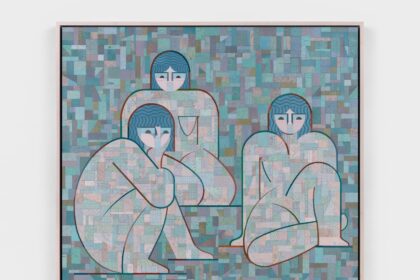その光景は、柔らかな光に包まれ、映画的でありながら、恐ろしいほどに陳腐だ。妊娠中の女性がスマートフォンをかざし、膨らんだお腹を母親に見せている。母親は息を呑んで喜び、赤ん坊をあやすような声を出し、母親としての助言を与える。しかし、その母親はすでにこの世にいない。彼女は、わずか3分間のビデオ映像から生成された、人工知能(AI)によって駆動するデジタル・マリオネット、「ホロアバター(HoloAvatar)」なのだ。
これは、元ディズニー・チャンネルのスター、カラム・ワーシー(Calum Worthy)が立ち上げた物議を醸す新アプリ、「2wai」が提示するプロモーション映像の一幕である。「3分間が永遠になる」と謳うその広告コピーは、ディストピアの予言が成就したかのような、冷たく金属的な重みを持って響く。2025年末、この映像がソーシャルメディアを駆け巡ったとき、人々の反応は感嘆ではなく、集団的な戦慄だった。即座に「悪魔的」「常軌を逸している」との烙印を押され、何千ものユーザーが、2013年のドラマ『ブラック・ミラー』における予言的なエピソード、「ずっと側にいて(原題:Be Right Back)」の筋書きを引き合いに出した。
だが、この現象を単に「不気味だ」と一蹴することは、現在進行中の深遠な存在論的転換を見落とすことになる。私たちは今、フランスの哲学者ジャン・ボードリヤールが「シミュラークルの先行」と呼んだ事態を目の当たりにしている。ボードリヤールの枠組みにおいて、シミュレーションはもはや現実を隠蔽するものではなく、現実を代替する。2waiのアバターは母親が死んだという事実を隠そうとはしない。その代わり、彼女の死が無意味となるような「ハイパーリアル(超現実)」なシナリオを構築するのだ。このアプリが提供するのは、地図(デジタルデータ)が領土(人間)を生み出し、死という有限性が、アルゴリズムによって修正されるべき技術的なバグとして扱われる世界である。
憑在論(ホントロジー)とデジタル・ゴースト
これらの「ホロアバター」が喚起する不安の正体を理解するには、テクノロジーの枠を超え、哲学の領域へと目を向ける必要がある。フランスの哲学者ジャック・デリダは、過去が完全に「現存(プレゼンス)」しているわけでも、完全に不在であるわけでもなく、「亡霊(スペクトル)」として持続する状態を記述するために、存在論(オントロジー)をもじった「憑在論(ホントロジー)」という言葉を作り出した。
AIによる「デッドボット(死者ボット)」は、究極の憑在論的人工物である。それはサーバーという「非場所(ノン・プレイス)」に常駐し、召喚されるのを待つ「デジタル・ゴースト」を生み出す。写真や手紙が「かつて・あった」ことの静的な記録であるのに対し、AIアバターは遂行(パフォーマティブ)的だ。それは現在形で語りかけ、時間軸の神聖さを侵害する。
ヴァルター・ベンヤミンはその記念碑的論考『複製技術時代の芸術作品』において、芸術作品の最も完璧な複製であっても、その「アウラ」――すなわち時間と空間における一回的な現存性――を欠いていると論じた。「グリーフボット(悲嘆ボット)」は、人間のアウラの最終的な破壊を象徴している。予測テキストアルゴリズムを通じて故人の人格を大量生産することで、私たちは個人からその固有の「いま・ここ」を剥奪し、人間の魂という名状しがたい火花を、確率論的なトークン(記号)のパターンへと還元してしまう。その結果生まれるのは「復活」ではなく、高解像度の空虚――芸術の領域から死者の領域へと移行したシミュレーションに他ならない。
「FedBrain」と人格という虚構
2waiのようなアプリの技術的アーキテクチャは、彼らが「FedBrain」(おそらく連合学習 Federated Learning への参照)と呼ぶ独自技術に依存している。これはユーザーのデバイス上で対話を処理することでプライバシーを確保し、「ハルシネーション(幻覚)」を低減すると主張するものだ。「ユーザーが承認したデータ」にAIを制限することで、アバターの真正性が保たれるという約束である。
しかし、大規模言語モデル(LLM)に関する最先端の研究は、これが誤謬であることを暴いている。研究によれば、LLMは人間の人格の複雑で安定した構造(「ビッグファイブ」特性など)を再現する能力を根本的に欠いている。また、LLMは「社会的望ましさのバイアス」――当たり障りのない、好感の持てる反応をする傾向――を抱えており、それはつまり、一人の人間をリアルな存在足らしめている、ギザギザとした扱いにくい特異なエッジを必然的に削ぎ落としてしまうことを意味する。
したがって、ユーザーは母親と交信しているのではない。母親の顔というマスクを被った、一般的で統計的なモデルと対話しているに過ぎない。「人格」は幻覚であり、「記憶」はデータベースだ。研究者たちが指摘するように、こうしたモデルには「身体化された経験」が欠落している。生存本能も、身体も、死すべき運命も――人間の認知を形成するあらゆる要素を持たないのだ。結果として生成される存在は*詐称者(インポスター)*であり、故ロビン・ウィリアムズの娘であるゼルダ・ウィリアムズが、父の同意なきAI再現について語ったように、「フランケンシュタインのような怪物」なのである。
喪の商業化:1,230億ドル市場
この技術的な降霊会を推進しているのは、強力な経済的エンジンだ。私たちは今、世界的に1,230億ドル以上の規模になると予測される「デジタル・アフターライフ産業(DAI)」、あるいは「グリーフ・テック(悲嘆テクノロジー)」の爆発的拡大を目撃している。
そのビジネスモデルは、批評家たちが「サービスとしての悲嘆(Grief-as-a-Service)」と呼ぶものだ。それは「喪に服す」という行為を、有限で共同体的なプロセスから、サブスクリプションに基づく無限の消費活動へと変容させる。
- 死者へのサブスクリプション:2waiや、(生前インタビューというより倫理的なモデルを採用している)HereAfter AIのような企業は、つながりへの渇望を収益化している。
- 「データイズム」の倫理: 哲学者のハン・ビョンチョルは、人間の経験が「データの全体主義」に屈服するデータイズムの台頭を警告している。この体制下では「デジタルの死」が否定される。私たちはデータを産出するゾンビとなり、墓の中からさえ収益を生み出し続けるのだ。
- 略奪的なメカニズム: ケンブリッジ大学の研究者たちが特定したリスクとして、「ステルス・マーケティング」がある。祖母の「デッドボット」が特定のブランドのクッキーを勧めてくる――これは最も脆弱な感情的絆を商業的利益のために悪用する、究極の説得的操作である。
悲嘆の神経科学:機械の中の「干渉」
哲学的、経済的な批判の先には、明白な心理的危険が横たわっている。アリゾナ大学の神経科学者であり、『The Grieving Brain(邦題未訳:悲嘆する脳)』の著者であるメアリー=フランシス・オコナー博士は、悲嘆とは根本的に学習の一形態であると提起する。
脳は、愛する人が永続的な固定要素(「私はいつもあなたのそばにいる」)として存在する世界地図を作成している。誰かが亡くなると、脳はその不在という新たな現実を反映させるために、苦痛を伴いながらこの地図を更新しなければならない。オコナーは、AI技術がこの重要な生物学的プロセスに「干渉する可能性がある」と警告する。常にインタラクティブな「存在のシミュレーション」を提供することで、グリーフボットは脳が喪失の教訓を学ぶのを妨げる。それは愛着の神経回路を、永続的で解決されない渇望の状態に留め置く――これは遷延性悲嘆症(Prolonged Grief Disorder)へのデジタルな処方箋となり得る。
法的空白地帯:「西部開拓時代」から「デジタル遺言」へ
私たちは現在、デジタルな死者の権利に関して、法的な「西部開拓時代」に生きている。米国では「死後のパブリシティ権」は継ぎ接ぎだらけで、多くの州では、自分の顔に対する権利は死んだ瞬間に消滅する。
一方、ヨーロッパは初期段階とはいえ、対照的な枠組みを提示している。例えばスペインは、データ保護法(LOPD)の中で「デジタル遺言(Testamento Digital)」の概念を先駆けて導入した。これは「デジタル相続権」を認め、市民が自身のデジタルフットプリントを管理または削除する特定の相続人を指名することを可能にするものである。
しかし、スペインの哲学者アデラ・コルティナが論じるように、規制は単に技術的なものであってはならず、倫理的なものでなければならない。問うべきは、誰がデータを所有するかだけでなく、死者に対してどのような尊厳が払われるべきか、ということだ。「デジタル遺体」は単なる資産ではない。それは生きた証の残骸である。死後にまで及ぶ強固な「ニューロライツ(神経の権利)」や「データの尊厳」に関する法律がなければ、死者に同意権はない。彼らは、2waiが構築を主張する「生きたアーカイブ」――企業が所有する魂の図書館――のための原材料となってしまうのだ。
沈黙の必要性
『ブラック・ミラー』の「アッシュ・ボット」の悲劇は、彼がアッシュのように聞こえなかったことではない。彼がアッシュのように聞こえてしまったことにある。それは完璧で空虚な反響を提供し、主人公を「保留された悲嘆」という屋根裏部屋に閉じ込めた。
「アルゴリズムの降霊会」は死を打ち負かすと約束するが、実際には喪のプロセスを打ち負かすことにしか成功していない。喪に服すこと、それは終わりを必要とする。それは沈黙を痛切に認めることを必要とする。私たちが生成AIのおしゃべりでその沈黙を埋めようと急ぐとき、私たちは深く人間的な何か――手放す能力――を失うリスクを冒している。データイズムとハイパーリアリティの時代において、最も過激な行為とは、死者をシミュレートすることも、サブスクリプションに登録することもなく、ただ安らかに眠らせておくことなのかもしれない。